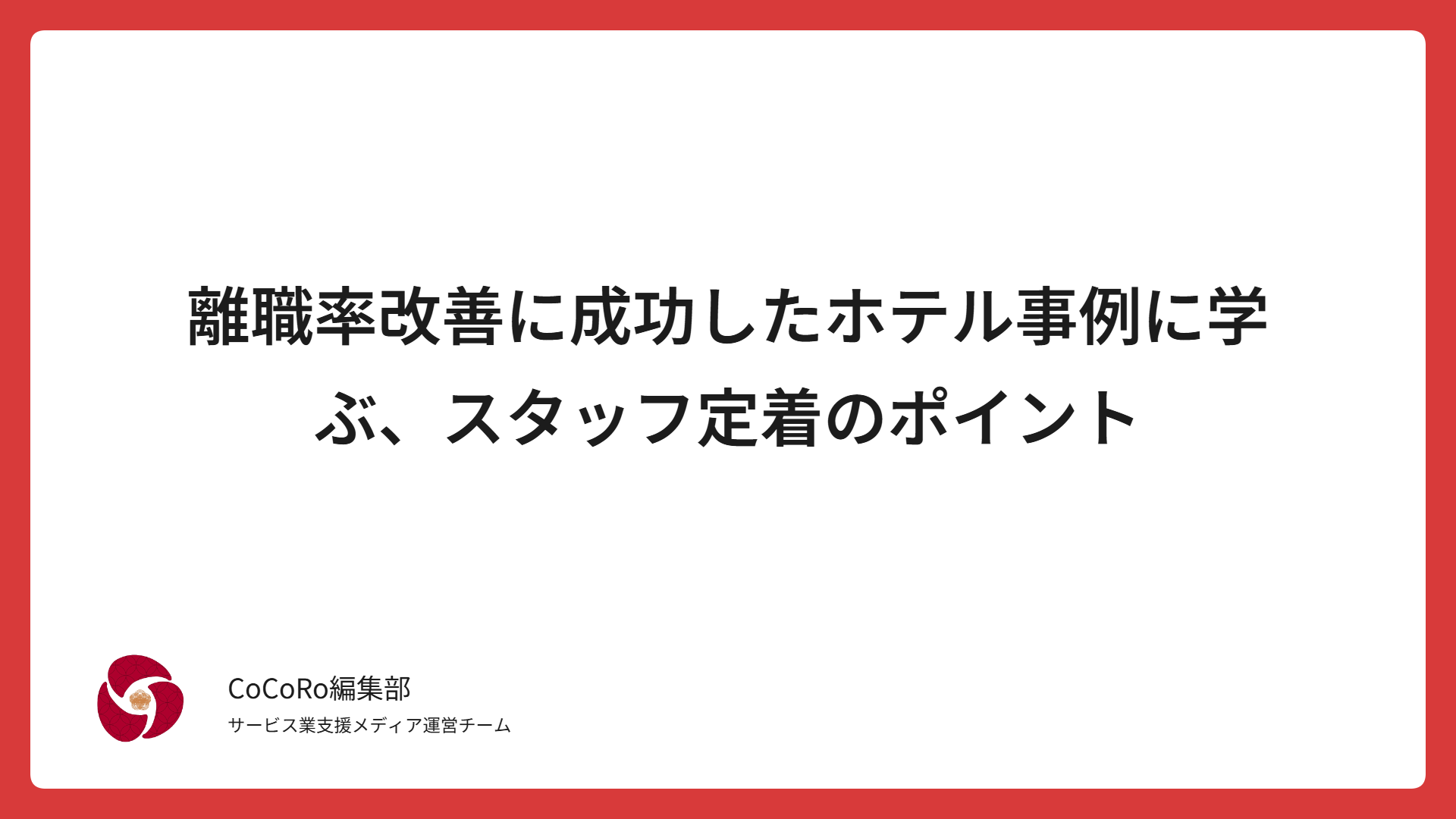
ホテル業界で離職率の高さに悩む方へ。離職率改善に成功した宿泊施設の具体的事例を紹介し、表彰制度や評価制度の見える化、福利厚生改革、組織風土改革といった共通の成功要因を体系的に解説します。若手や外国人スタッフが「辞めずに残る」職場づくりのヒントが満載です。
はじめに:ホテル業界の離職率と人材定着の課題
ホテル・宿泊業界は全産業の中でも離職率が高いことで知られています。厚生労働省の調査によれば、2023年の宿泊業・飲食サービス業の離職率は26.6%(全産業中2位)にも上り、人手不足と高離職率が深刻な経営課題となっています。長時間労働や休暇取得の難しさ、低賃金といった労働環境の厳しさが背景にあり、「人が定着しない」悪循環に頭を抱える支配人の方も多いでしょう。
こうした課題を踏まえ、ピラーページ「ホテル業界の離職率が示すヒント: 人が残る環境とは?」では業界全体の離職率の現状や原因を詳しく解説しました。本記事ではさらに踏み込み、離職率の改善に成功した具体的なホテル・旅館の事例をご紹介します。
それらの事例から浮かび上がる共通の成功要因(表彰制度の導入、評価制度の見える化、福利厚生の改革、組織風土の改革)を体系立てて整理し、若手スタッフや外国人スタッフが辞めずに活躍し続ける職場づくりのポイントを探っていきます。離職率改善に取り組むヒントとして、ぜひ自社の状況と照らし合わせながらご覧ください。
離職率改善に成功した宿泊施設の共通点とは?
離職率の低下やスタッフ定着率向上を実現した宿泊施設の事例を紐解くと、スタッフのモチベーションやエンゲージメントを高めるための工夫が随所に見られます。その共通点を大きく4つに分類すると以下の通りです。
- 表彰制度の活用(頑張りを正当に称える)
- 評価制度の「見える化」(評価基準を明確にし納得感を与える)
- 福利厚生・待遇の改革(働きやすい環境と公正な報酬)
- 組織風土の改革(コミュニケーション活性化とエンゲージメント向上)
以下では、それぞれのポイントについて具体的な成功事例を交えながら詳しく解説します。
1. 従業員を正当に称える「表彰制度」の導入
スタッフの努力や成果をきちんと評価し、表彰という形で称える仕組み作りは、モチベーション向上と離職防止に効果的です。多くの宿泊施設で、社内表彰制度の導入が人材定着の鍵となった事例があります。
たとえばある老舗旅館では、社内コミュニケーション活性化の一環として定期的な社内イベントや優秀従業員の表彰制度を取り入れました。従業員アンケートで意見を積極的に集めるなど現場の声も反映した結果、従業員満足度が向上し定着率アップに貢献しています。表彰によって社員一人ひとりの頑張りが認められることで承認欲求が満たされ、「もっと頑張ろう」という意欲につながるためです。
外国人スタッフの定着という観点でも、表彰制度は有効に機能しています。大手ホテル清掃事業会社の事例では、インドネシア人の技能実習生を多数受け入れ育成する中で、毎年全社表彰で実習生が選出され社内報にも掲載されるそうです。
実習生たちにとっても自分の努力が認められ社内で表彰されることは大きな励みとなり、仕事への誇りとモチベーションにつながっています。現地に帰国後も「日本で表彰された経験」を家族や周囲に発信するケースもあり、本人のキャリア形成にも好循環を生んでいるとのことです。
このように、優れたサービス提供者を定期的に称える仕組みは、従業員の承認欲求を満たし組織への愛着心を育む効果があります。表彰制度の導入によって「頑張ればきちんと認められる」という風土が醸成され、結果として離職率の低下につながった例は少なくありません。
実際、あるビジネスホテルでは社内表彰や従業員同士で感謝を伝え合うサンクスカード制度を導入し、従業員を称賛する文化を育てたことで職場満足度と定着率の向上を実現しています。
▶ポイント: 表彰制度を形骸化させないためには、評価基準を明確にし公平性を担保することが重要です。誰にでもチャンスがあり納得感のある表彰であれば、社員のモチベーション喚起に直結します。小さな成果や日頃の努力にもスポットライトを当て、「あなたを見ている、きちんと評価している」というメッセージを送ることが、特に若手や異国から来たスタッフのエンゲージメント向上につながるでしょう。
2. 「見える化」された評価制度がもたらす納得感
離職理由の一つに「評価があいまい・不公平」という不満があります。そこで、評価制度を透明化・客観化して納得感を高める取り組みが有効です。成功事例では、定量的な指標やフィードバックを用いて従業員の働きを「見える化」し、公平な人事評価につなげています。
例えば千葉県のあるリゾートホテルでは、客室清掃スタッフの生産性や清掃品質をデータで見える化できるシステムを導入しました。スタッフごとの清掃時間やミス発生率を記録・可視化し、客観的な評価指標として活用できるようにしたのです。
その結果、個々のスタッフの働きぶりが数値で把握できるようになり、公正な人員配置や評価が可能となりました。可視化されたデータに基づき人事評価制度の基礎を構築できたことで、近い将来には具体的な待遇改善(成果に応じた報酬や昇進)にもつなげる見込みだといいます。
このように属人的・主観的になりがちなサービス現場の評価をテクノロジーで見える化することは、スタッフの納得感を高めるうえで大きな効果があります。
また、お客様からの声を評価に取り入れる仕組みも注目されています。従来、ホスピタリティ業務では「お客様に直接褒められる」「クレームをもらう」以外に自分の接客の良し悪しを知る機会が少なく、手応えを感じにくい面がありました。
そこで登場したのが、ゲストからスタッフ個人宛に感謝のメッセージとチップ(心づけ)をデジタルで届ける新しい仕組みです。「CoCoRo(ココロ)」というサービスでは、宿泊客が気に入ったスタッフを指名してスマートフォン経由でメッセージとオンラインチップを送ることができます。
受け取ったスタッフ側は、その感謝メッセージを自分への評価として実感できますし、マネージャーも「誰がどんな褒め言葉をいただいたか」を把握できるため、人事評価や表彰の材料とすることができます。
メッセージ例: 「◯◯さん、素敵なおもてなしをありがとうございました。あなたのおかげで両親との記念旅行が最高の思い出になりました!」
(※このような感謝の言葉がお客様から直接スタッフ本人に届きます)
実際に兵庫県のグリーンヒルホテルではCoCoRoを試験導入しており、支配人の方は「スタッフ宛に届いたお客様のメッセージや心づけが会話のきっかけとなり、『○○さんすごいね、どんなことしたの?』とスタッフ同士で称え合う文化が生まれサービス品質向上につながっていく」ことに期待を寄せています。
お客様が感じた「嬉しいポイント」が具体的にフィードバックされることで、スタッフに当事者意識が芽生え、自分の強みや良かった点を自覚するきっかけにもなるといいます。あるマネージャーは「スタッフそれぞれの頑張りを知れるのは管理者としても嬉しい」と語っており、従業員のモチベーション向上策として手応えを感じています。
このようなデジタル心づけシステムは、日本ではまだ新しい取り組みですが着実に広がりつつあります。2023年4月のサービス開始以来、「CoCoRo」は大手チェーンホテルやリゾートホテル、旅館など30施設以上で導入が予定されており、多言語対応(英語・中国語・韓国語)によって訪日外国人からの感謝もダイレクトに受け取れる点が評価されています。
社内アンケートでも「チップやお客様からのメッセージは仕事のやりがいにつながる」と感じるスタッフが約90%にのぼったとのデータもあり、前向きなインセンティブ効果が伺えます。
▶ポイント: 評価制度の見える化には、「数値目標の設定」「顧客満足度など定量フィードバックの活用」「第三者評価の導入」など様々なアプローチがあります。重要なのは、スタッフが自分の貢献度合いや成長を実感できる仕組みを作ることです。
定量データや顧客の声によるフィードバックを組み合わせることで、感情的・属人的な評価への不満を和らげ、公平で納得感のある評価文化を醸成できます。それが結果的に「報われている」と感じられる職場環境につながり、離職率の低下に寄与します。
3. 働きやすさを追求した「福利厚生・待遇改革」
離職率改善の基本は、何より待遇を見直すこと――多くの成功事例がまず口を揃えるポイントです。ホテル業界全体が労働時間や給与水準で低い水準にある中で、「業界平均並み」で満足していては人材流出に歯止めはかかりません。優秀な人材に「この職場に留まりたい」と思ってもらうには、業界標準以上の魅力的な働きやすさを提示する努力が不可欠です。
給与・勤務制度の見直し
離職防止策としてまず効果が大きいのが給与待遇の改善です。あるホテルチェーンでは、コロナ禍後の人材確保戦略として新人事制度の導入に踏み切りました。この「社員がChoiceできる人事制度」では、社員自らが希望勤務エリアを都道府県単位で選択できるようにし、転勤に伴うライフスタイルの不安を解消しました。
さらにライフイベント(結婚や介護等)に合わせて働き方を柔軟に変えられる仕組みを整えた結果、導入1年で離職率が前年比2%低下(16.34%→14.27%)し、内定辞退者も大幅減少(73%減)するなど確かな効果が現れています。また応募者数も飛躍的に増え、人材確保にも好影響が出ています。
この事例では、社員が自分の働き方を「選択」できる公平感が定着につながったと分析されており、「主体的に選んだ範囲で働けることで納得度が上がった」ことが離職率改善の一因とされています。
同社では元々、年2回の7連休取得制度を20年以上前から導入し、有給休暇を取りやすいシフト運用を行うなど、先進的なリフレッシュ制度にも取り組んできました。24時間営業が当たり前のホテル業にあっても計画的に長期休暇を取得できる環境を整え、心身のリフレッシュを重視していたのです。
こうした働き方改革の積み重ねが社員の定着率向上に寄与し、コロナ禍後に導入した前述の勤務地選択制度と相まって、同社の離職率は着実に改善傾向を見せています。
他にも、離職率改善に成功した宿泊施設では給与テーブルの見直し(成果やスキルを正当に評価した昇給・賞与制度)や柔軟なシフト制度(連休や希望休の取得を推進)などに踏み切った例が多く見られます。
業界水準よりも高めの給与レンジを提示したり、深夜手当・宿直手当を充実させることで、「待遇が不満で辞める」という動機を根本から潰すわけです。また社宅提供や社員食堂の整備、福利厚生クラブ加入といった生活面の支援を強化し、「この会社で働き続けるメリット」を感じられるよう工夫している企業もあります。
若手・外国人スタッフへのキャリア支援
「将来の展望が描けない」「成長機会がない」と感じると、人は離れていきます。そこで従業員のキャリア形成を支援する制度も重要です。成功事例の宿泊施設では、資格取得支援制度や階層別研修制度の充実によって社員のスキルアップを後押しし、長期的なキャリアパスを提示しています。たとえば「5年後にマネージャー」「将来的にソムリエなど専門職にもチャレンジできる」といった明確なキャリアパスを示すことで、若手社員が将来像を持って働ける環境を作っています。
特に昨今増えている外国人スタッフに対しては、日本語教育や資格取得支援、正社員登用制度などキャリアアップの道筋を用意することが定着率アップに直結します。ある企業では、技能実習生として来日した外国人を正社員に登用し、将来的には本国での現地法人スタッフや自社グループ内で昇進のチャンスを与える仕組みを設けています。
また、日々の業務の中で小さな成功体験を積ませ自信を育むことも大切です。前述のように、外国人スタッフを積極的に表彰したり、等級制度(明確なグレード制度)によって「あなたは今○級、次のレベルまであと一歩」といった目標設定をわかりやすく可視化している企業もあります。
これにより、異国の地で不安を抱えがちなスタッフにも努力の方向性と達成感を提供し、働き続ける意欲を高めています。
▶ポイント: 福利厚生・待遇の改革にはコストも伴うため悩ましいところですが、「人に投資する」発想が結果的に離職率改善による採用コスト削減やサービス向上による業績アップとなって返ってくることを成功事例は示唆しています。まずは自社の労働環境を客観的に診断し、業界平均と比べて遜色のない魅力を備えているかチェックすることが肝心です。その上で、可能な範囲で待遇改善に踏み切る大胆さが求められます。例えば「同地域他社より●円高い時給」や「年間休日●日保証」など具体的な打ち手により、働く側にとって魅力的な職場づくりを目指しましょう。
4. 風通しの良い組織風土づくりとエンゲージメント向上
最後のポイントは、職場の文化・風土そのものを改革し、従業員エンゲージメントを高める取り組みです。給与や制度が整っていても、日々働く現場の雰囲気が悪かったり人間関係が希薄だと、人は定着しません。成功したホテル・旅館は総じて「人を大切にする企業文化」を育み、従業員が働きがいを持てる環境づくりに力を入れています。
コミュニケーション活性化と現場の声の尊重
組織風土改革の第一歩は、社内のコミュニケーションを活発にし経営層と現場の距離を縮めることです。京都のある企業では、社内SNSアプリを導入して社長自ら日々情報発信を行い、スタッフ間の双方向コミュニケーションを促進しました。
その結果、導入前に課題だらけだった組織診断の結果が改善し、離職率も約80%減少したといいます。トップが現場にメッセージを届け、従業員の声にも耳を傾けるようになったことで、「会社に大切にされている」と感じる社員が増えたのが大きな要因でした。
また、老舗旅館の事例では若手スタッフが中心となって社内情報共有プラットフォームを運用し始めたところ、ベテラン勢も巻き込んで世代や部署を超えたコミュニケーションが活発化しました。これにより引き継ぎ業務が円滑になったり、お互いの苦労や工夫を理解し合うことで職場の一体感が醸成されたそうです。
上司との1on1ミーティングの定期実施やメンター制度(新人に先輩が相談役として寄り添う)の導入に踏み切ったホテルもあり、従業員が孤立せず何でも相談できる雰囲気作りが奏功しています。
さらに、「従業員の声を経営に反映する仕組み」も重要です。定期的な従業員満足度調査や意見箱を設置し、現場からの提案を積極的に採用するホテルでは、従業員のエンゲージメント(愛着心・貢献意欲)が明らかに向上しました。自分たちの意見で職場が良くなる経験は、「この会社で頑張りたい」という気持ちを強めてくれます。
感謝と称賛の文化を根付かせる
組織風土改革において見逃せないのは、お互いに感謝し称え合う前向きな文化を育むことです。前述の表彰制度もその一環ですが、日常的なレベルでもサンクスカード(従業員同士で「ありがとう」のメッセージを送り合う仕組み)や朝礼でのグッジョブ発表など、小さな称賛を積み重ねる施策が有効です。
リゾートホテル運営会社の例では、スタッフ間で良い行いを見つけたらカードで感謝を伝える取り組みを始めたところ、職場の雰囲気が明るく変わり新人定着率が向上しました。「誰かが自分をちゃんと見ていて、認めてくれる人がいる」と実感できる職場は働いていて嬉しいものです。
大和ライフネクスト株式会社のケースでは、清掃現場で働く技能実習生を含む全スタッフに対し「ほめて育てる」文化を浸透させました。前述の通り、実習生を社内表彰したり社内報で称賛を紹介するほか、日々の業務でも成果を上げたらすぐ周囲で讃える風土づくりに努めています。
同社の担当者は「教育と評価制度の両輪で人材の成長につなげている」と述べており、叱責よりも称賛を重視する業界慣習への挑戦が成果を上げているようです。運送業界の別企業でも「怒られてばかりで褒める文化がない」という常識を変えるため、褒め言葉を贈り合う社風への転換を図った結果、毎年30%だった離職率が10%未満にまで改善した例があります。「褒める」ことはコストがかからず明日からでも始められる最良のマネジメント策と言えるでしょう。
▶ポイント: 組織風土改革は一朝一夕には成し遂げられませんが、小さな施策の積み重ねがやがて大きな成果となります。従業員同士がお互いを思いやり、助け合い、高め合う文化を育てることで、「この仲間と働き続けたい」という気持ちが芽生え、離職の抑止力となります。経営層はまず模範を示す形で現場に寄り添い、感謝と言葉掛けを惜しみなく実践しましょう。風通しの良さを感じられる職場は、働く人にとってかけがえのない居場所となるはずです。
おわりに:人が「残り続ける」職場を目指して
離職率の高止まりに苦しむホテル・宿泊業界ですが、見方を変えれば人材定着のためにできる工夫はまだまだ多く存在することが成功事例から見えてきます。
本記事で紹介したように、表彰制度によるモチベーションアップ、評価制度の透明化による納得感、福利厚生改革による働きやすさ向上、組織風土改革によるエンゲージメント向上──これらはいずれも「人を大切にする」職場づくりの具体策と言えます。
大切なのは、自社の課題を正確に見極め、ブレない軸を持って施策を講じることです。離職率改善は短期で結果が出にくい領域ですが、一つひとつの取り組みが積み上がれば必ず効果は表れてきます。
実際に、複数の対策を講じたホテルでは「採用コストの削減」「サービス品質向上による売上増」といった副次的なメリットも生まれています。人材が定着し現場が安定すれば、顧客満足度も向上し、ひいては経営指標全般が好転する好循環が期待できます。
自社の労働環境を客観的に診断してみたい方は、まず無料の「労働環境診断」ツールを活用して現状を把握してみましょう。診断結果から課題が見えたら、ぜひ本記事で取り上げたような成功事例を参考に改善策を検討してみてください。
人が「辞めない」で「活躍し続ける」職場には、必ず理由があります。離職率が示す課題に真摯に向き合い、スタッフ一人ひとりが「ここで働いてよかった」と心から思える環境を作ることができれば、きっと離職率の数字も好転していくはずです。人財が定着する魅力ある職場づくりに向けて、できる一歩からぜひ着手してみてください。
