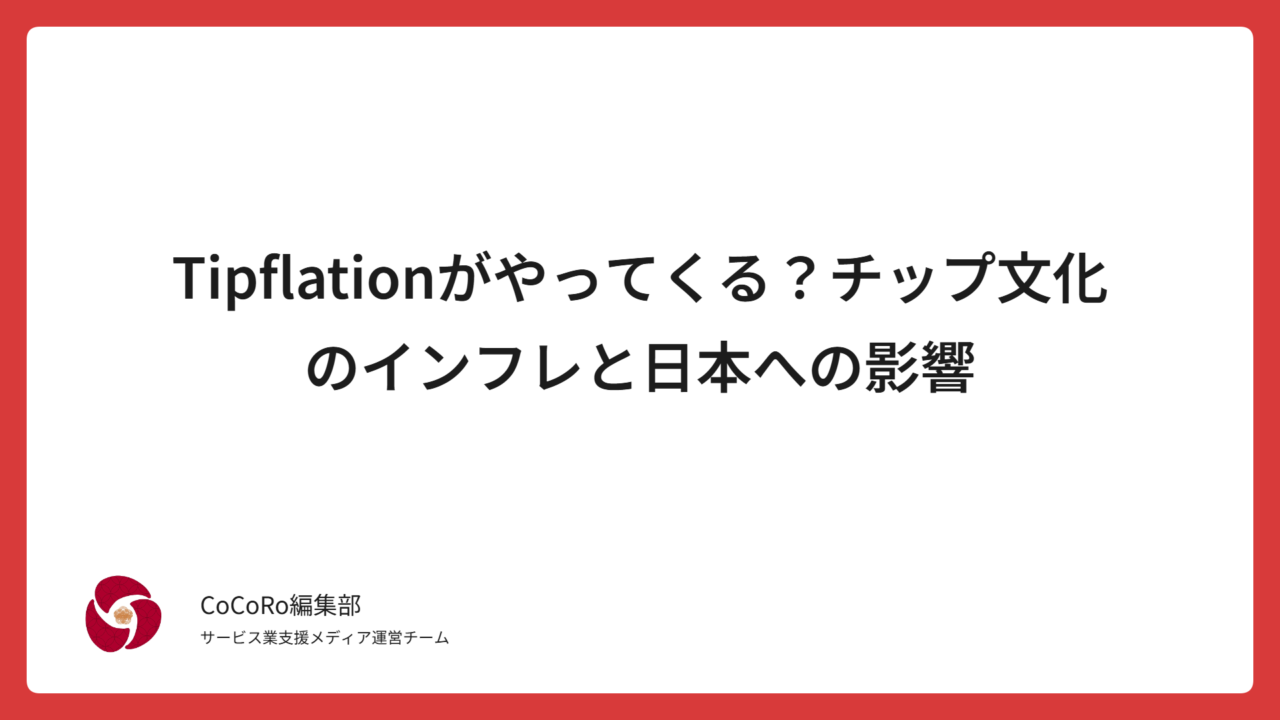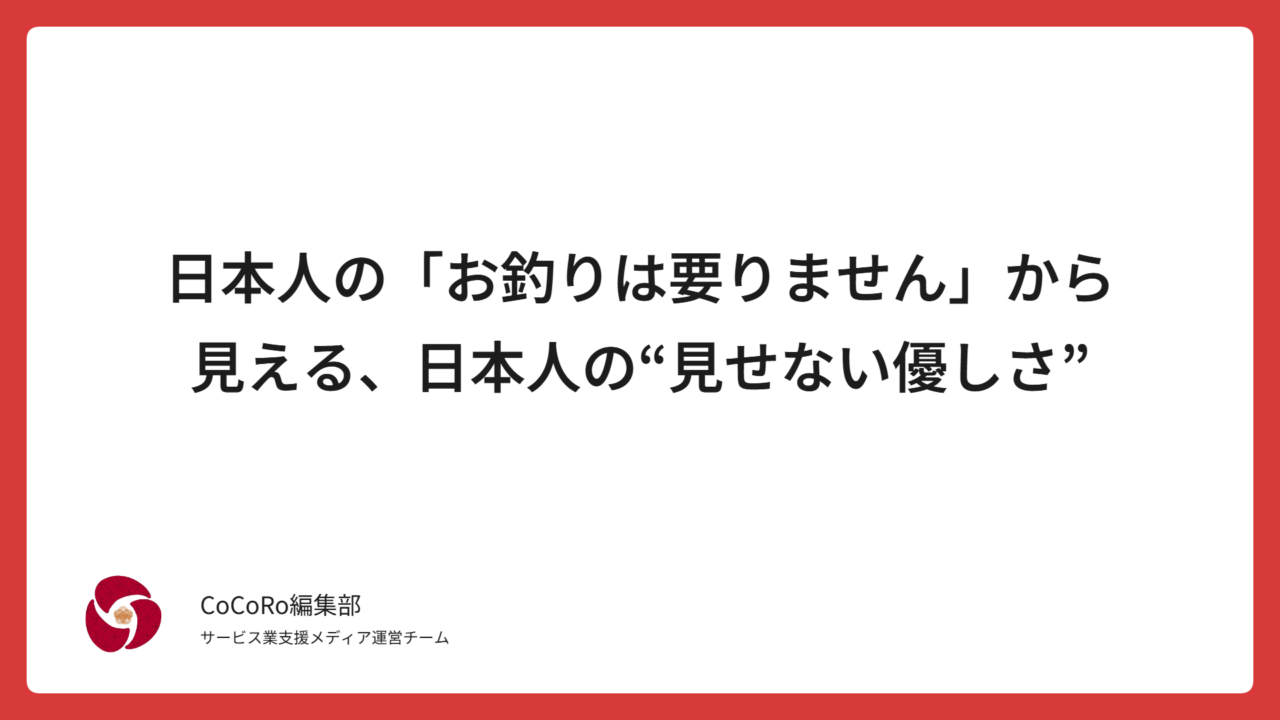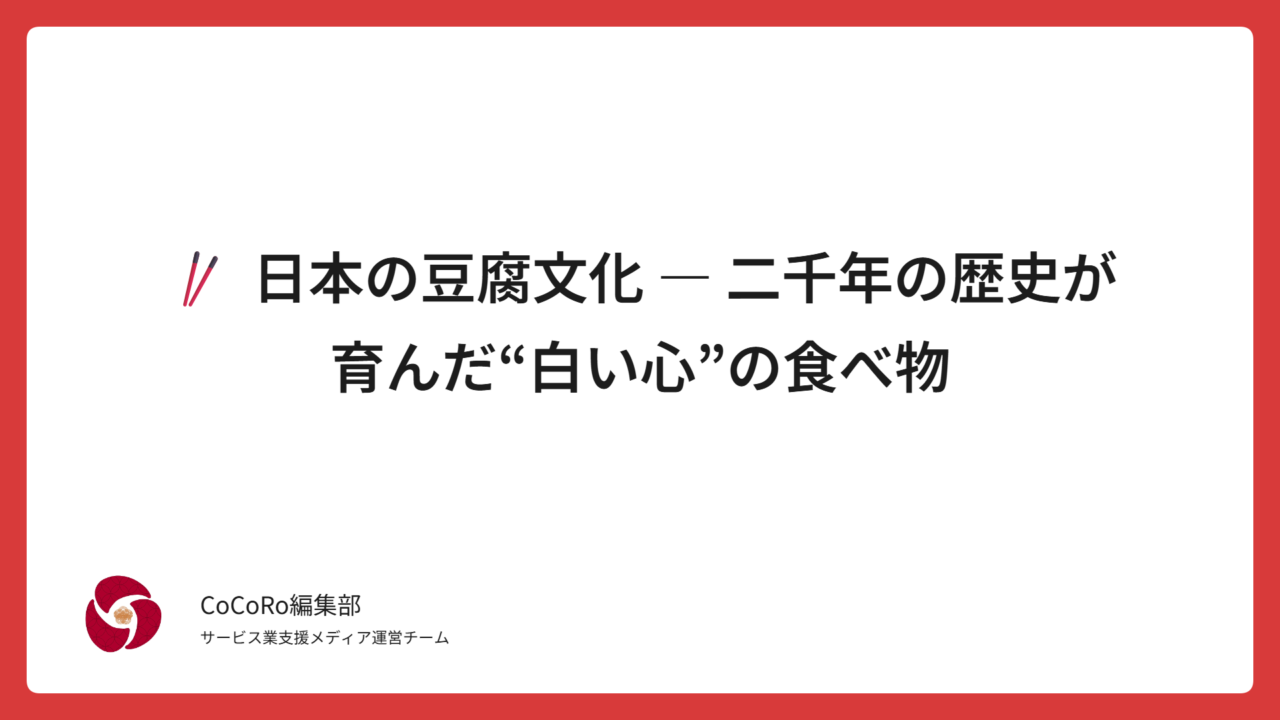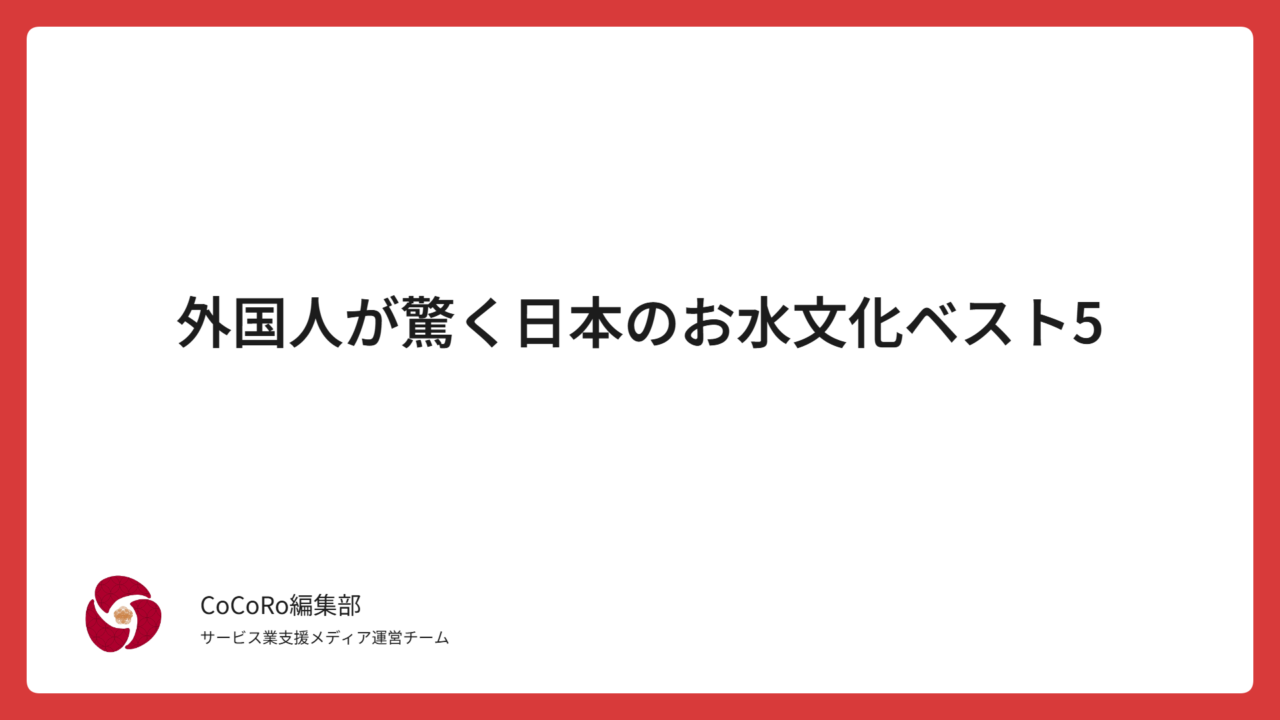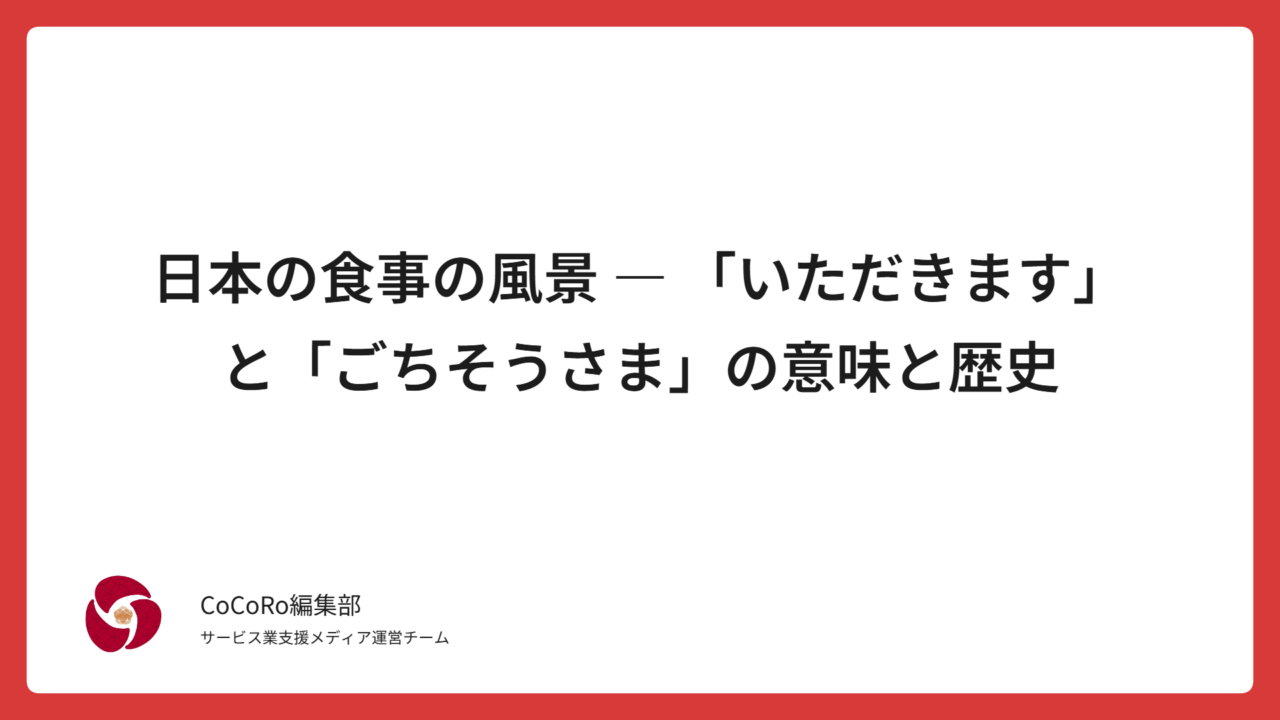

日本人が食事の前後に言葉を添える理由
日本では、食事の前に「いただきます」、食べ終えた後に「ごちそうさまでした」と言う習慣があります。
日常的な挨拶として当たり前のように使われていますが、
改めて考えると「なぜ言うのか」「誰に向けて言っているのか」は意外と知られていません。
この二つの言葉は、単なるマナーや形式ではなく、
日本人の価値観や歴史、そして他の文化との違いを映す鏡のような存在です。
本稿では、「いただきます」と「ごちそうさま」の意味と起源、
そして現代に至るまでの変化を、文化と教育の観点から見ていきます。
第1章:「いただきます」の意味と起源
「いただきます」とは何か
「いただきます」という言葉は、動詞「いただく」から生まれました。
もともとは「頭上に載せて受け取る」という動作を指し、
目上の人から物や恩恵を受ける際の謙譲表現として使われてきました。
やがて、食事の際に「自然の恵み」や「作ってくれた人」から
食べ物を“いただく”という意味に広がっていきます。
つまり、「いただきます」は単なる開始の合図ではなく、
“命や恵みを受け取る”ことへの敬意を表す言葉へと変化していったのです。
食前の挨拶として定着するまで
現代では当たり前のこの挨拶も、
日本の長い歴史の中で見ると比較的新しい習慣です。
江戸時代や明治初期には、食前に「いただきます」と言う習慣はほとんど見られず、
むしろ「黙して食べる」ことが礼儀とされていました。
これは、食事を神聖な行為と捉え、
静寂の中で自然や命への感謝を表す文化的背景があったためです。
つまり、かつての日本人にとって“感謝とは言葉ではなく態度で示すもの”でした。
第2章:「ごちそうさま」の由来と意味
「ごちそう」の語源
「ごちそう」は、漢字で「馳走」と書きます。
もともと「走り回る」という意味を持ち、
人をもてなすために食材を集め、調理に奔走する姿から生まれた言葉です。
したがって「ごちそうさま」とは、
“その奔走に感謝します”という意味であり、
料理を作ってくれた人へのねぎらいの言葉です。
外でも家庭でも使われる日本独自の礼
かつては「ごちそうさま」は外食や他家での食事の際に使われる言葉でした。
しかし、戦後の社会では家庭内でも使われるようになり、
日常の礼儀として広く浸透していきます。
現代の日本では、飲食店を出る際に
「ごちそうさまでした」と店員に伝える人も多く、
これは単なる挨拶以上に、人の労を言葉で労う文化的特徴といえるでしょう。
第3章:沈黙の礼から言葉の感謝へ ― 教育による定着の歴史
「黙して食べる」ことが美徳だった理由
古くから日本では、食べ物には“命”や“霊”が宿ると考えられてきました。
神道や仏教の影響を受け、食事は自然の恵みをいただく神聖な行為とされてきたのです。
そのため、食事中に無駄な言葉を控え、
静かに箸を進めること自体が感謝の表現とされました。
また、武士の家では、食事も礼法の一部でした。
主君の前での無駄口は無礼とされ、沈黙は「統制」や「品格」の象徴。
庶民の間でも、家族や仲間が黙って囲炉裏を囲み、
“共に食べること”そのものが絆を作るとされていたのです。
1934年 ― 「いただきます」が教育に登場する
食事の前後に挨拶を添えるという考え方が、
日本で初めて文献として登場するのは1930年代です。
1934年、西川文子の著書『ハイハイ学校提唱講話』にはこう記されています。
「御飯はいただきますで始め、ごちさうさまで終りませう。
食べものに好き嫌ひを云はぬやう叮嚀にかみこぼしたり、
御膳をよごさぬ樣にしませう。」
この記述は、食前・食後の挨拶を明確に指導する最古の文献として知られています。
つまり、「いただきます」「ごちそうさま」は、
道徳教育の中で意識的に広められた文化だったのです。
戦後、全国へ広がった「食の挨拶」
この習慣が全国に定着したのは、戦後の学校教育によるものです。
食糧難の中で始まった学校給食は、
「食べられること」への感謝を子どもたちに教える場でもありました。
食前の「いただきます」、食後の「ごちそうさま」は、
“食べることのありがたさ”を共有するための小さな儀礼として根づき、
戦後教育の一部として全国に広まりました。
この時期の「いただきます」は、
まだ“命への感謝”という哲学的な意味までは含まれておらず、
食べ物・作り手・社会への敬意を言葉で示す礼儀として理解されていました。
第4章:「命への感謝」という考え方の誕生
食育と道徳教育の中での変化
1970〜1980年代になると、学校教育やテレビ番組などを通して、
「命をいただく」という考え方が広がります。
食育の現場では「食べ物は誰かの命」「残さず食べることが感謝」というメッセージが強調され、“命への感謝”が「いただきます」の中心的な意味として定着していきました。
この流れは、高度経済成長によって
「食べ物が簡単に手に入る時代」になったことへの反動でもありました。
飽食と浪費の中で、「感謝を取り戻す」教育が求められたのです。
総合的な感謝の言葉へ
現代では、「いただきます」は単に食材や命に対してだけでなく、
生産者、流通、調理、そして家族など、
食に関わるすべての存在への感謝を含む言葉として捉えられています。
「ごちそうさま」も同様に、
“食事を支えてくれたすべての人と環境”に向けた感謝の言葉へと拡張されました。
言葉の形式は変わらなくても、
その中に込められた意味は時代とともに深まっているのです。
第5章:海外から見た「いただきます」と「ごちそうさま」
海外の人々が初めて「いただきます」を知るきっかけは、
日本のアニメやドラマの食事シーンであることが多いと言われています。
登場人物が手を合わせて「いただきます」と言う姿に、
“日本の礼儀正しさ”を感じたという声は少なくありません。
ただし、海外の「祈り(grace)」とは意味が異なります。
多くの国では神に感謝を捧げる宗教的儀式ですが、
日本の「いただきます」は特定の信仰を持たない世俗的な感謝の表現です。
自然、社会、人の営み――そのすべてに向けて、静かに感謝を示す言葉なのです。
終章:言葉がつなぐ、感謝のかたち
「いただきます」と「ごちそうさまでした」は、
日本人が日常の中で大切にしてきた“感謝の言葉”です。
かつては沈黙で表していた礼が、
教育とともに言葉の形で受け継がれ、
やがて「命への感謝」という普遍的な価値へと発展しました。
この二つの言葉は、
食卓という小さな場所から生まれた、
日本人の“心の作法”といえるでしょう。
形式でも強制でもなく、
「今日も食べられること」そのものへの静かな感謝。
それが、現代の「いただきます」と「ごちそうさま」に込められた本当の意味です。