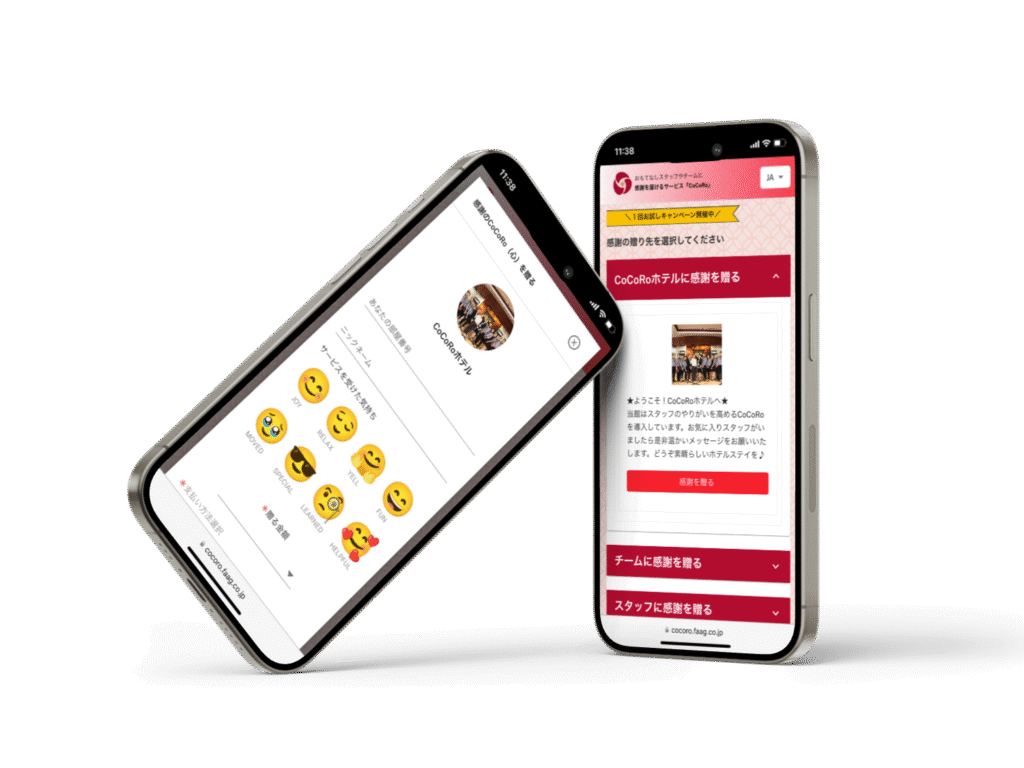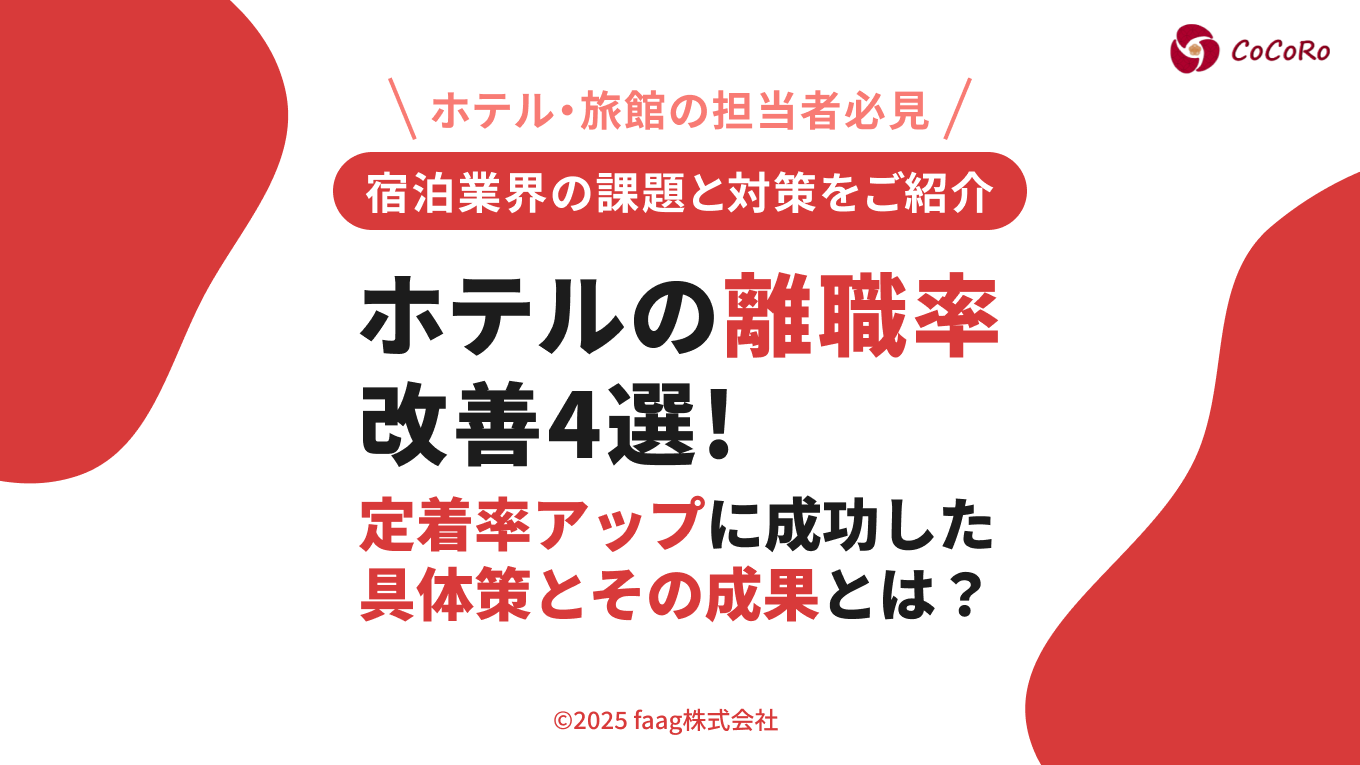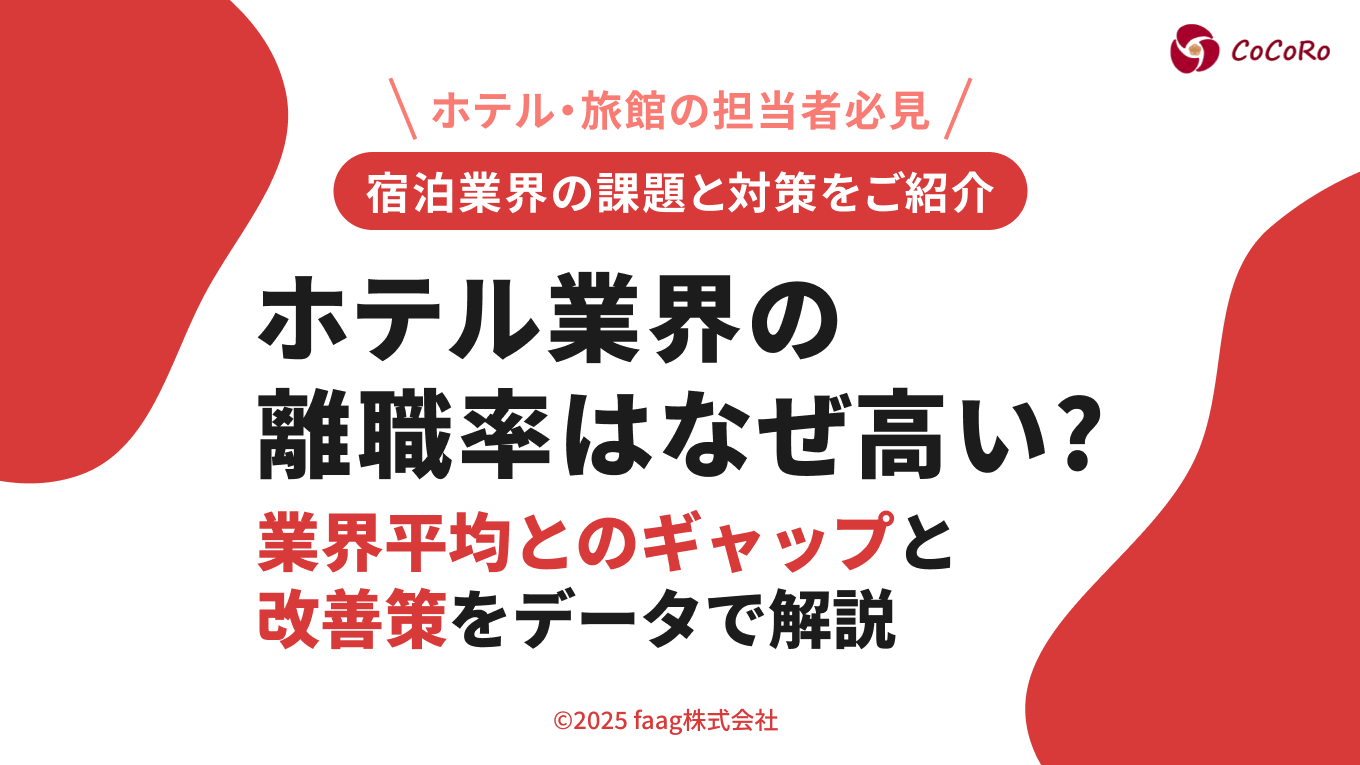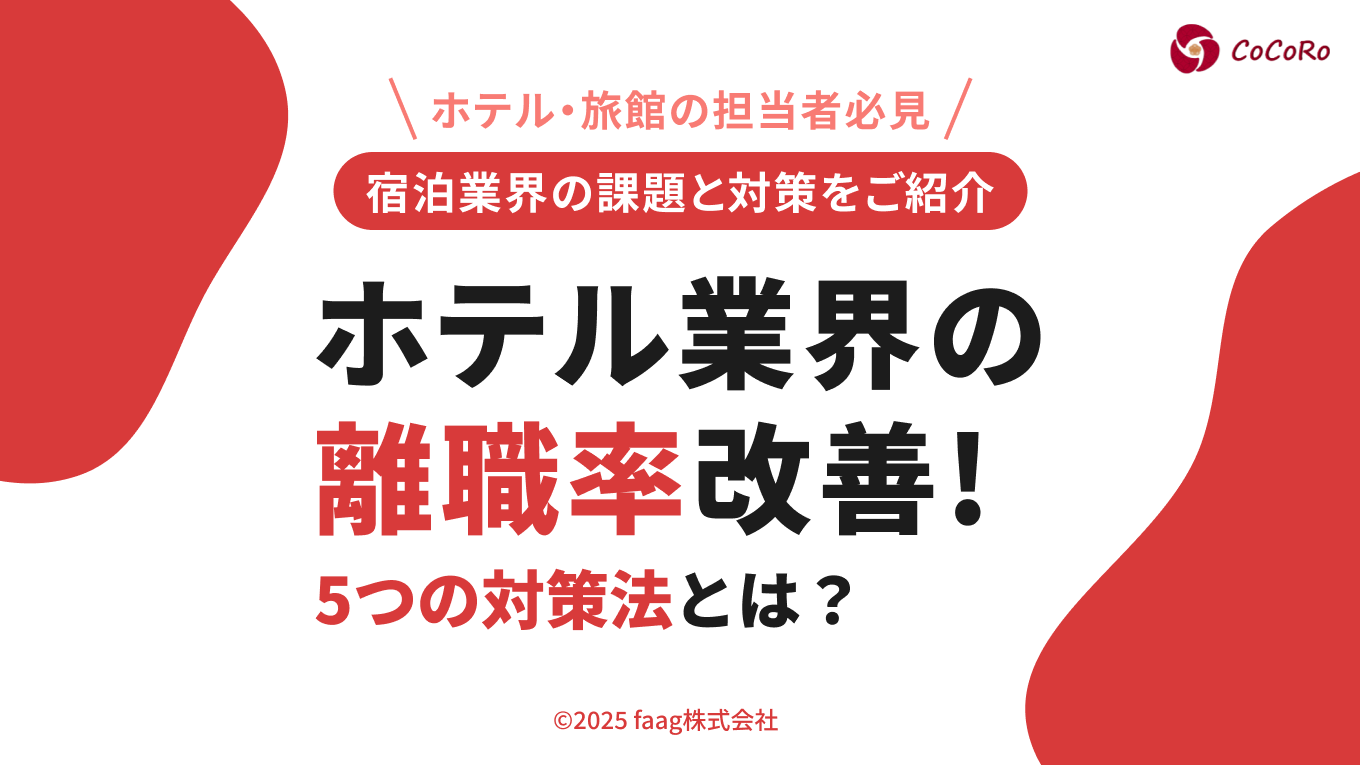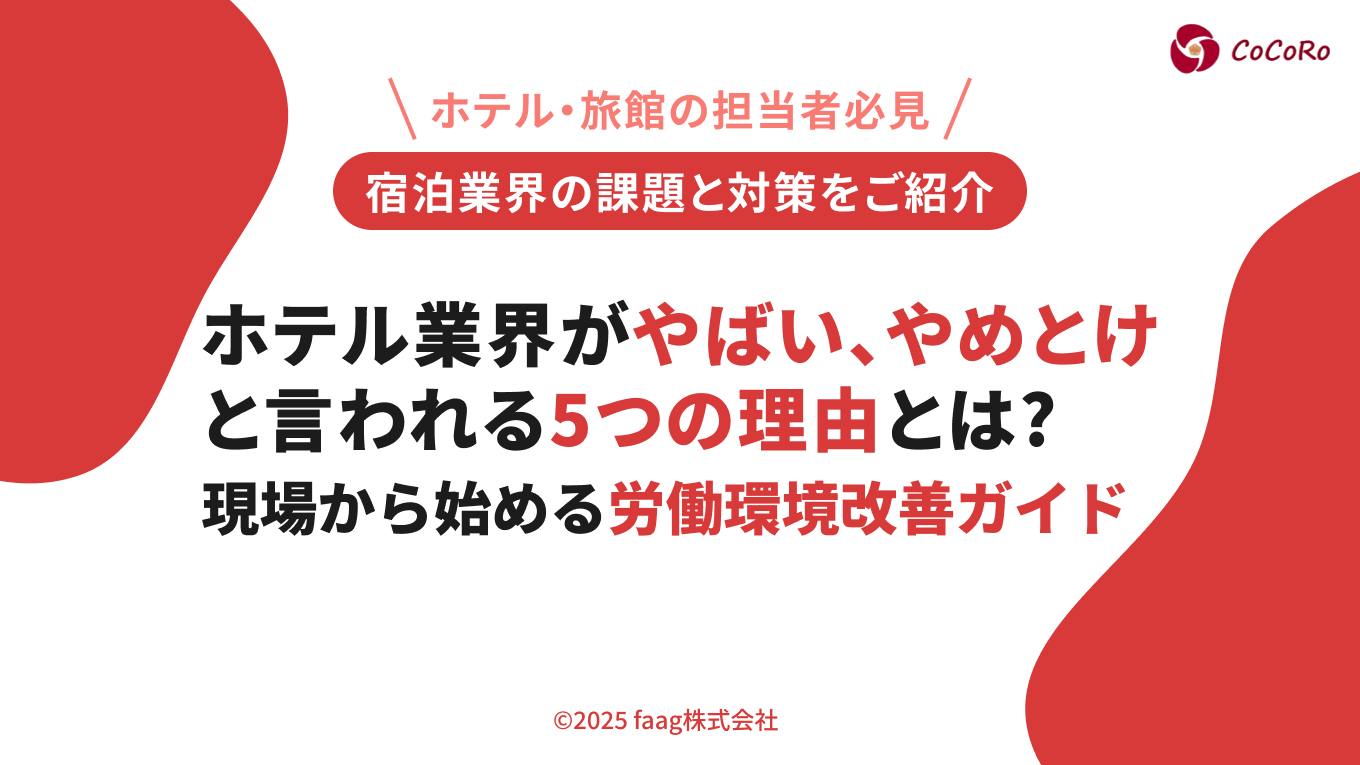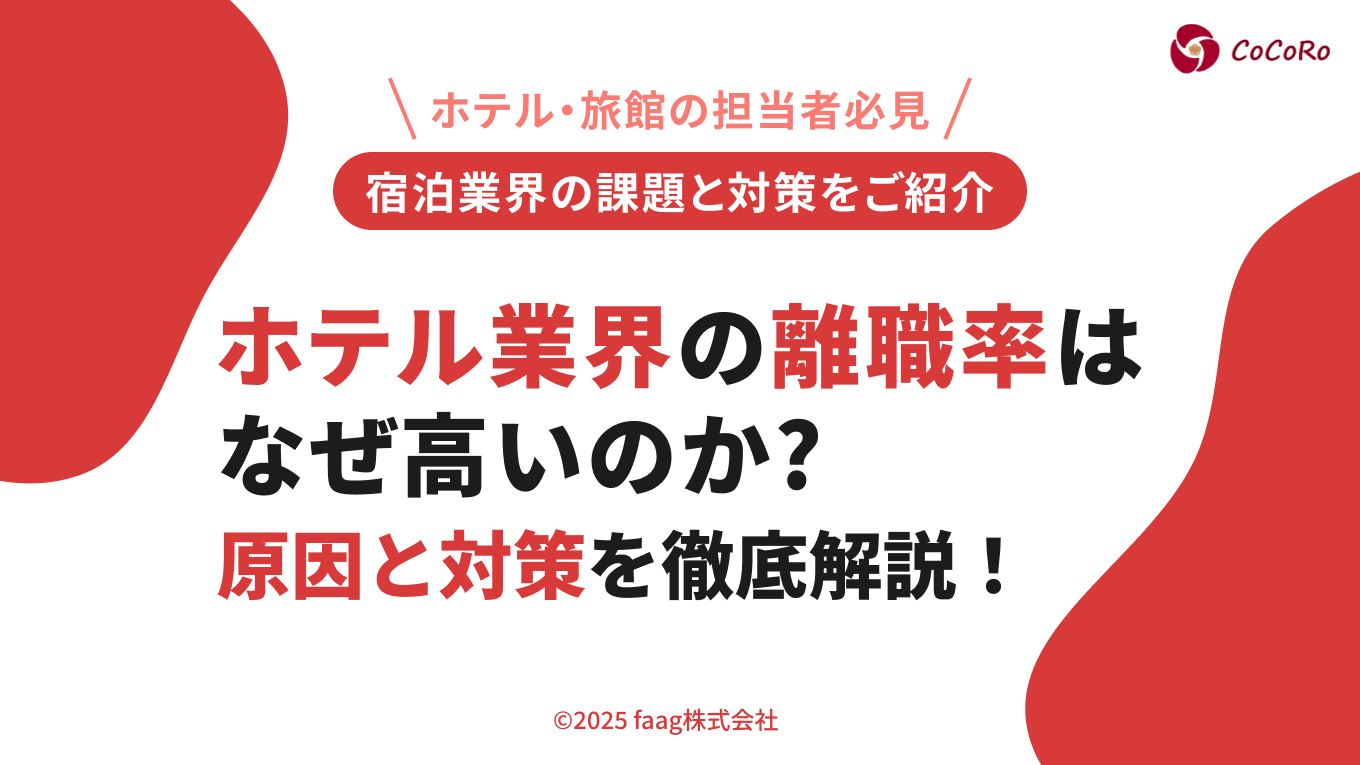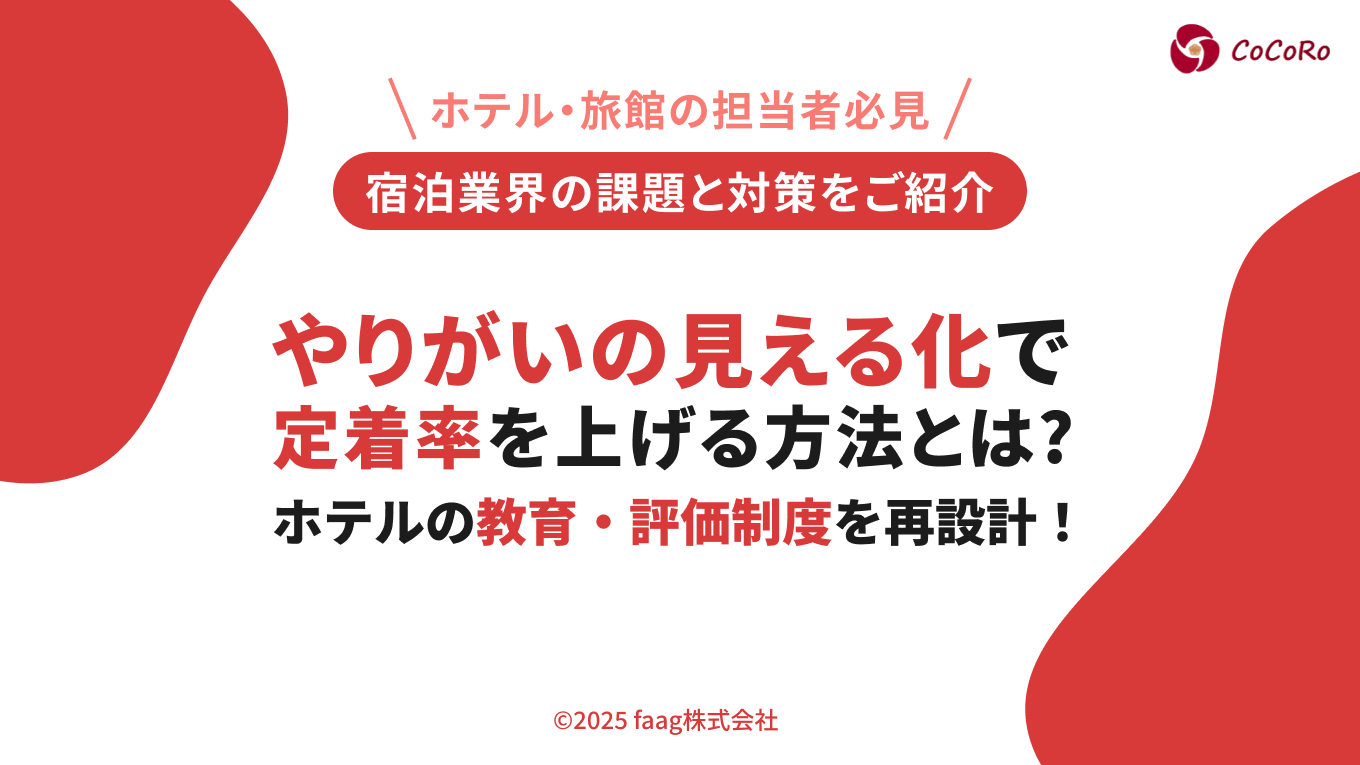
はじめに:離職の裏にある「評価されない」実感
ホテル・宿泊業界では、若手スタッフの早期離職が大きな課題となっています。実際、宿泊業の離職率は全産業中でも突出して高く、厚生労働省の雇用動向調査(令和5年)によると宿泊業の離職率は25.6%と最も高水準でした。給与や長時間労働といった要因に加え、「自分が正当に評価されていないのでは」という不安や不満が離職の背景に潜んでいるケースも少なくありません。この課題に目を向け、特に若手が辞めない職場づくりの第一歩として、ホテル業界の教育・評価制度を見直す必要があります。
).png)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/kekka_gaiyo-02.pdf,(参照:2025年7月8日).
ホテル業界における教育・評価制度の課題
現場のスタッフ教育や人事評価の仕組みには、従来からいくつかの課題が指摘されています。ここでは特に「評価の偏り」「属人的な教育」「成長実感の欠如」という3つのポイントに着目し、宿泊業界特有の問題を整理します。
定性的な評価に偏る現場評価
サービス業であるホテルの現場では、おもてなしの質やホスピタリティといった数値化しづらい要素が評価の中心になります。その結果、どうしても 主観に頼った定性的評価に偏りがち です。現場の上司それぞれの印象で評価が決まってしまい、評価者によって基準がばらつくケースも少なくありません。たとえば明確な評価指標が無いまま、「あのスタッフは頑張っている」「この新人はまだまだだ」といった属人的な判断が行われていれば、スタッフは自分がどこまで成長したのか実感できず不安になります。
一方、売上高や件数などの定量的な指標はフロントスタッフや現場業務では限られており、評価に反映しづらい現状があります。そのため目標設定も曖昧になり、「とにかくお客様に尽くすように」など抽象的な評価項目に終始しがちです。定性的な評価だけでは客観性に欠け、公平な比較も難しいため、スタッフから見ると「何を頑張れば評価されるのか」が見えにくくなります。このような評価制度のままでは、努力が報われないと感じてモチベーションを失う恐れがあります。
OJT頼みの属人化と教育コストの非効率
新人育成に目を向けると、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に頼りきりの体制が目立ちます。多くのホテルでは先輩社員が後輩に付き添って仕事を教えていますが、これは裏を返せば 教育の質が先輩の能力や熱意に左右される ことを意味します。体系だった研修プログラムが整備されておらず、「現場で見て覚える」が当たり前になっている職場も多いでしょう。
しかし、属人的なOJTにはいくつかの問題があります。まず、指導内容の標準化・均質化が難しいため、教える人によって新人の習熟度に差が出てしまいます。熱心な上司に当たれば良いのですが、忙しさに追われ指導が後回しになるケースでは新人は十分な学習機会を得られません。また、教育担当となる先輩社員にとっても負担が大きく、自分の業務と指導の両立で疲弊してしまう恐れがあります。
さらに、人手不足の深刻な現場では「新人にじっくり教える時間がない」ことも深刻です。十分な研修期間もなく現場投入せざるを得ないケースでは、新人は右も左も分からないまま業務をこなすことになりがちです。これは新人にとって大きなストレスであり、「ちゃんと教えてもらえない」「自分は役に立っていないのでは」といった不安から早期離職につながるケースもあります。属人的で非効率な教育体制を放置すれば、人材育成に時間がかかるだけでなく、せっかく採用した人材を失う悪循環に陥ってしまいます。
参考:国土交通省 観光庁 令和6年度「宿泊業の人材確保・育成の状況に関する実態調査事業」報告書
成長実感・達成感が持ちにくい仕組み
評価制度や教育体制の問題は、最終的にスタッフ本人の成長実感の乏しさに帰結します。定性的な評価ばかりで基準が不明瞭な職場では、「自分は評価されているのか」「どのくらい成長できたのか」が本人にも掴みにくく、達成感を得にくいものです。加えて、宿泊業界では明確なキャリアパスが描きにくいという構造的課題も指摘されています。現場一筋の働き方になりがちで、「この先のキャリアの展望が見えない」と感じる若者も多いのです。
また、日々の業務においてお客様からのポジティブなフィードバックを得る機会が少ないことも見逃せません。クレーム対応などネガティブな声は耳に入ってきやすい一方で、「ありがとう」「また来ます」といった感謝の言葉は本人に十分伝わらないまま終わっていませんか? 現状では多くの宿泊施設で、お客様の声を体系的に収集・共有する仕組みがなく、スタッフは自分の接客が本当に役立っているのか実感しづらい状況に置かれています。「この接客で良かったのか?」という疑問を抱えたままでは、モチベーションも上がらず、仕事のやりがいを見失ってしまいます。
以上のように、ホテル業界の現行の教育・評価の仕組みには若手の成長意欲ややりがいを阻む構造的な課題があります。労働条件(賃金・勤務時間など)の問題と相まって、これらが離職の要因となっているのです(※教育・評価以外の「労働環境の5課題」については別記事「労働環境の5課題」で詳しく解説しています)。では、定着率を高めるためには具体的にどのような評価制度へと転換すれば良いのでしょうか?
定着率を高めるための評価制度とは?

上記の課題を踏まえ、若手スタッフの定着率向上につながる評価・教育の仕組みを考えてみましょう。キーワードは「可視性」と「納得感」です。スタッフが自らの成長と貢献を実感でき、正当に評価されていると納得できる制度こそが、やりがいを醸成し離職を防ぎます。そのために有効なアプローチを3つ紹介します。
定量・定性の両面評価の導入
まず取り組みたいのは、定量評価と定性評価をバランス良く組み合わせることです。売上やKPI達成率など数値で表せる成果については定量的に評価し、接客態度やチームワークなど数値化しにくい部分は定性的に評価する、といった具合に両面から評価指標を設定します。定性的な項目についても評価基準書を作成し、具体的な行動例を示すことで主観のブレを抑えます。一方、定量的な目標も設定しやすいものはできるだけ導入し、誰が見ても分かる客観的な指標を評価の一部に組み込みます。
例えば、フロント業務であれば「チェックイン手続きの平均所要時間」や「会員登録件数」など、工夫次第で数値目標を設定できる分野があります。ハウスキーピングでも「清掃後の客室インスペクション合格率」など測定可能な指標があります。こうした定量目標の達成度は本人の努力の結果として視覚化できるので、評価に取り入れることでスタッフのモチベーションと納得感が高まります。定量・定性の両面評価を導入することで、「結果もプロセスも見てもらえている」という安心感が生まれ、評価への不満を減らすことが期待できます。
お客様の声をフィードバックとして活用
次に重要なのが、お客様の声(VOC:Voice of Customer)を評価・教育に活かす仕組みづくりです。具体的には、宿泊客から寄せられるアンケートコメントやサンキューメッセージ、口コミ評価などを積極的に収集し、現場スタッフへフィードバックします。ポジティブなフィードバックはスタッフにとって大きな励みとなり、「自分の努力が報われた」という実感を与えます。たとえ小さな「ありがとう」の一言であっても、直接その声を聞くことで即座に承認欲求が満たされ、達成感を感じられるのです。
例えば、お客様アンケートで「◯◯さんの笑顔のおもてなしに感動しました!」というコメントがあれば、それを該当スタッフに共有するだけでなく、朝礼や社内報で紹介して全員で称賛する、といった仕掛けが考えられます。社員は自分の存在価値を実感し、職場全体も明るい雰囲気になります。心理学的にも「感謝されること」は幸福感や自己肯定感を高め、離職防止に効果的だとされています。特に若手社員にとって、第三者(お客様)からの評価は「自分もこの会社でやっていける」という自信につながり、その積み重ねがやりがい向上・定着率向上に寄与します。
重要なのは、こうしたポジティブな声を人事評価にも組み込むことです。具体的には、半年や年次の評価面談の際に「◯◯さんはお客様から○件の感謝コメントをいただいています」とフィードバックし、定性的評価の裏付けデータとして活用します。お客様の声をエビデンスにすることで、従来は評価しづらかったホスピタリティ精神や気配りといった面を適切に評価できるようになります。また、お客様の声を社内表彰制度と連動させ、「お客様満足度賞」「ありがとう賞」のような表彰を行えば、現場の士気向上とサービス改善の好循環を生み出せるでしょう。
“やりがい”を数値化するには
最後に、仕事のやりがいを「見える化」する取り組みについて考えてみます。やりがいとは本来主観的なものですが、工夫次第で定量的な指標として捉えることが可能です。鍵となるのは、スタッフが感じる貢献実感をデータとして蓄積することです。
例えば、あるスタッフがお客様から月に10通のサンキューメッセージを受け取ったとします。この「10通」という数は、そのスタッフが生んだ感動や満足の数として捉えられます。言い換えれば、「ありがとう」を数えることでやりがいの量を測っているのです。実際、宿泊業で働く人を対象とした調査でも、「チップやお客様からのメッセージは仕事のやりがいにつながる」と感じている人が約90%にも上りました。このデータは、スタッフがどれだけお客様に喜ばれているかを数値で示すことが、本人のやりがい向上に直結することを示しています。
では具体的にどう数値化するか。手段の一つが専用のプラットフォームを導入することです。例えば、お客様からのメッセージとお心づけ(チップ)をデジタル収集できる「CoCoRo」のような仕組みを使えば、誰が何件の感謝を受け取ったか、月々いくらのチップを獲得したかといったデータが自動で蓄積されます。そのデータをスコアや指標として人事評価に組み込めば、「◯◯さんはやりがいスコアが社内トップ」といった形でやりがいを可視化・数値化することが可能です。

重要なのは、数値化したやりがい指標を評価や面談でフィードバックし、スタッフ自身に「あなたの貢献度はこれだけ数字に表れていますよ」と伝えることです。これにより、スタッフは自分の成長や貢献を客観的に認識でき、さらなる意欲向上につながります。やりがいの見える化は、評価制度再設計の中核と言えるでしょう。
教育と評価の再設計が定着を生む:5つの改善ポイント

以上、ホテル業界の人材定着に向けて「教育」と「評価」の仕組みを見直すポイントを解説してきました。最後に、定着率を高めるために押さえておきたい5つの改善ポイントを整理します。
- 評価基準の明確化と統一
属人的な評価を廃し、客観的かつ統一された評価基準を設ける。評価者研修の実施や評価シートの整備で、誰が評価しても大きなブレがない仕組みにする。スタッフに「何をすれば評価されるか」が明示されることで納得感が生まれる。 - 定量指標の導入と目標管理
売上や件数だけでなく、サービス品質に関する定量KPIを開発・導入する。例:顧客アンケートの満足度スコア、リピーター率、会員登録件数など。数値目標を設定し達成度合いを評価に反映することで、努力の結果が見えるようになりモチベーション向上につながる。 - お客様の声の収集・共有
VOCを体系的に収集する仕組みを構築し、ポジティブな声は即座に本人とチームにフィードバックする。感謝の言葉や高評価コメントは社内報告や朝礼で共有し、組織全体で称賛する文化を醸成する。「嬉しいお客様の声」を社内表彰や評価項目に組み入れ、スタッフのやる気とエンゲージメントを高める。 - OJT+OFF-JTのハイブリッド育成
現場OJTに加え、研修(OFF-JT)の計画的な実施で新人育成の効率と質を向上させる。忙しくても最低限の座学やロールプレイ研修を用意し、指導担当者へのトレーニングも実施する。新人が「教えてもらえないまま現場に放り出される」状況を無くすことが離職防止に直結する。研修で得た知識と現場経験を組み合わせ、成長を加速させる仕組みづくりを。 - キャリアパスの明確化と成長支援
現場スタッフが将来の自分の姿を思い描けるよう、人事制度上のキャリアパスを整備する。昇進要件やジョブローテーションの機会を示し、「〇年後にはリーダーに」「支配人への道もある」といった希望が持てるようにする。また、スキルアップ支援制度(資格取得支援や社外研修参加推奨など)を導入し、「学び直し・成長できる職場」という安心感を与える。スタッフが自己成長を実感できれば、組織へのエンゲージメントも高まり定着率向上につながる。
これら5つのポイントを実践することで、スタッフにとって「ここで働き続ければ明るい未来が描ける」と思える職場環境が築かれます。評価と教育の再設計は決して容易なミッションではありませんが、着実に取り組めば現場スタッフの意識と行動に変化が表れます。その結果、サービス品質が向上し、お客様満足度やリピート率の上昇、ひいては事業業績の向上にもつながっていくでしょう。
まとめ:スタッフの未来を描ける制度を
若手スタッフの離職に悩むホテル業界において、「仕事のやりがいが見える職場づくり」は避けて通れないテーマです。教育と評価の仕組みを再設計し、スタッフの貢献を正しく評価・称賛する制度を整えることで、社員一人ひとりが仕事の意義を実感し、成長意欲を持って働ける環境が生まれます。それはすなわち、スタッフが自分の未来をこの職場に重ね合わせられるようになるということです。
「人」が重要な資産であるホテル業界だからこそ、従業員のエンゲージメント向上(特に仕事のやりがいと組織への貢献意欲の向上)は事業成長の大きな鍵となります。評価制度を見直し、やりがいを可視化する取り組みは、スタッフの定着率アップのみならず顧客満足度や企業イメージの向上にも波及します。ぜひこの機会に、自社の教育・評価の仕組みを点検し、スタッフの未来を共に描ける制度へとアップデートしていきましょう。現場で輝くスタッフの笑顔こそが、お客様の笑顔とホテルの繁栄を生み出す原動力になるのです。